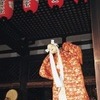京都のお寺・神社で節分祭
ご自宅で「鬼は外!福は内!」の豆まきだけじゃない、京都のお寺・神社での節分行事をご紹介いたします。
-
 吉田神社
吉田神社
貞観元年(西暦859年)に、平安京の守護神として創建され、厄除け開運の神様として親しまれている神社で、境内には重要文化財の大元宮も。 また室町時代よりつづく節分祭は、伝統の一大行事です。
- 住所:京都市左京区吉田神楽岡町30番地
- アクセス:市バス「京大正門前」より徒歩5分
京阪「出町柳」駅より徒歩20分 - 電話番号:075-771-3788
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:なし
- 価格帯:無料
-
 八坂神社
八坂神社
- 住所:京都市東山区祇園町北側625 075-561-6155
- アクセス:市バス「祇園」下車すぐ
京阪「祇園四条」駅より徒歩5分
阪急「河原町」駅より徒歩8分 - 電話番号:075-561-6155
- 休業日:なし
-
 霊山観音
霊山観音
【創建・由緒】 昭和30年6月8日、平和日本の建設と殉国の英霊並びに大戦による犠牲者の冥福を祈念するため、故・石川博資氏により建立。
- 住所:京都市東山区高台寺下河原町526-2
- アクセス:市バス「東山安井」より徒歩7分
京阪「祇園四条駅」より徒歩15分 - 電話番号:075-561-2205
- 営業時間:8:40~16:20(16:00受付終了)
- 価格帯:一般/200円(線香付き)
高校生以下/150円(線香なし)
-
 松尾大社
松尾大社
上古の庭 曲水の庭 蓬莱の庭
- 住所:京都市西京区嵐山宮町3
- アクセス:阪急「松尾大社」駅より徒歩3分
市バス・京都バス「松尾大社前」より徒歩3分 - 電話番号:075-871-5016
- 営業時間:平日・土曜 9:00~16:00 日祝日 9:00~16:30
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/500円
中・高・大学生/400円
小人/300円
-
 神泉苑
神泉苑
回遊式 舟遊式
- 住所:京都市中京区御池通神泉苑東入門前町166
- アクセス:市バス・京都バス「神泉苑」下車すぐ
地下鉄「二条城前」駅より徒歩2分 - 電話番号:075-821-1466
- 営業時間:8:30~20:00
- 休業日:無休
- 価格帯:無料
-
 金閣寺(鹿苑寺)
金閣寺(鹿苑寺)
室町幕府3代将軍・足利義満が公家の山荘を譲り受け、北山殿を造営したことを起源とし、義光の死後、禅寺に改め義満の法号をとって鹿苑寺と名付けられた。 衣笠山・左大文字山を借景とした池泉回遊式・舟遊式庭園(特別名勝・特別史跡)。 約6600㎡の鏡湖池(きょうこち)には神仙思想が取り入れており、蓬莱島(葦原島)、鶴島、亀島など大小の島や、諸大名に贈られた各地の名石も配されている。 三尊石組・九山八海石・護岸石組が見られ、港に停泊する船を表現した夜泊石もある。 また龍門の滝も有名。鯉が滝を登ると龍になるといわれる中国の故事・登竜門にちなみ、滝の下には鯉に見立てた鯉魚石が置かれている。 その他、金森宗和作の茶室・夕佳亭、四つ目垣の変形種・金閣寺垣、足利義満が手植えしたと伝えられる陸舟の松など。
- 住所:京都市北区金閣寺町1
- アクセス:市バス「金閣寺道」
- 電話番号:075-461-0013
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/400円
小・中学生/300円
-
 千本ゑんま堂 引接寺
千本ゑんま堂 引接寺
【創建・由緒】 高野山真言宗。小野篁(おのの たかむら)が開基。寛仁期、恵心僧都の法弟、定覚(じょうかく)上人が創建。 百人一首の歌人として知られる小野篁(802~853)は、この世とあの世を行き来する神通力を有したとされており、昼は宮中に赴き、夜は閻魔之廰に仕えたとの伝説を残している。 篁は閻魔法王より現世浄化のため、塔婆を用いて亡き先祖を再びこの世へ迎える供養法で、後に我が国の伝統習慣である「盂蘭盆会(お盆行事)」へと融合発展する法儀「精霊迎えの法」を授かった。その根本道場として、朱雀大路(現・千本通り)の北側に篁自ら閻魔法王の姿を刻み建立した祠が、開基とされる。
- 住所:京都市上京区千本通寺之内上る閻魔前町34番地
- アクセス:市バス「千本鞍馬口」より南へ徒歩すぐ
市バス「乾隆校前」より北へ徒歩すぐ - 電話番号:075-462-3332
- 営業時間:境内参拝自由
- 休業日:無休
- 価格帯:境内参拝自由
-
 西陣・くらしの美術館 冨田屋
西陣・くらしの美術館 冨田屋
明治期に建てられ、国の登録有形文化財・京都市重要景観建造物にも指定されている貴重な京町家のお屋敷です。 町家の見学から、着付け体験やお茶席体験、マナースクールなど、京都の文化に触れられる体験ができます。
- 住所:京都市上京区大宮通一条上ル
- アクセス:市バス「一条戻り橋」「今出川大宮」より徒歩3分
- 電話番号:075-432-6701
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:年中無休
-
 壬生寺
壬生寺

- 住所:京都市中京区壬生梛ノ宮町31
- アクセス:阪急「大宮駅」より徒歩4分
嵐電「四条大宮駅」より徒歩4分
市バス「壬生寺道」下車すぐ - 電話番号:075-841-3381
- 営業時間:境内自由(8:30~16:30) ※庭園は通常非公開
- 休業日:無休
- 価格帯:境内自由